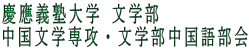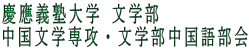【内容紹介】
Amazonのカスタマーレビュー
「ヤヤー」さんの書き込みより
十八歳の頃、自分は何を考えていたんだろう。 少なくとも、食べる心配はしていない。・・・受験? それだって、今思えばそれほど真剣じゃなかった。 ただ、自分が生まれ育った家から出て行くことだけは決めていたけれど。 それも、親が何もかもしてくれるとわかっていた。 だから、隣の国で何が起こっていたのかなんて知らなかったし、興味もなかった。自分と同世代の人間が、食うや食わずの生活をしていたなんて!しかもあの中国で、料理の歴史も華やかな国で!まるで戦時中のような生活の様子に、信じられない思いで読んだ。自分の出自を呪うということはこういうことなのかと思う。きめ細やかな愛情にあふれた日常生活など、六六(リュウリュウ)には望むべくもなかった。国の、党の政策に従って家族を作り、国民としての義務を果たすことを強制され、それでも必死に生きている底辺の人々。しかしながら、そのスラムこそが六六の人となりを作り上げたのだ。淡々とした語り口とは裏腹の、激しい女の半生である。
Amazonのカスタマーレビュー
「ようこ」さんの書き込みより
小道具ではない描写は、ずしずしと目の前に映像として迫ってきます。早く言えば、悲惨なスラムの暮らし、読むのをためらいながらも、先を読まずにいられない筆力。ぜひ、多くの女性に読んでいただきたい。
Amazonのカスタマーレビュー
「F1フリーク」さんの書き込みより
タイトルが気になって、購入してしまいました。なんとも心が痛い、胸に詰まるような思いです。何の苦労も無い私たちが、こんな境遇を想像なんて出来ません。すべてが過剰で、有り余る生活をしている私たちに突きつけられる、大きな課題です。皆さん是非読んで何かを感じ取ってください・・・。う~ん・・・上手く説明できない。
|